
2009年11月21日(土)、「第10回東京フィルメックス」が開幕した。初日には、千代田区神田駿河台の明治大学アカデミーホールにて、「第10回記念シンポジウム <映画の未来へ>」が行われ、映画監督の北野武氏、黒沢清氏、是枝裕和氏と俳優の寺島進氏、西島秀俊氏が、それぞれの視点から映画の未来について語った。 最初に登場したのは、北野武監督(聞き手は映画評論家の山根貞男氏。また、急遽、オフィス北野社長でプロデューサーの森昌行氏も登壇)。『その男、凶暴につき』(1989)でのデビュー以来20年余、現在、2010年公開予定の新作を製作中の北野氏は、視聴者が無料で見ることのできるTVとは異なり、料金を払って観にきてくれる観客のことを思うと、映画では妥協することができないと語り、起用した俳優の演技が気に入らず編集でバッサリとカットしてしまったことや、現場では、出演俳優からの演出への口出しを好まないことなど、自身の映画製作にまつわるさまざまなエピソードを、時に、非常にシビアな横顔を覗かせつつ笑いも交えてサービス精神たっぷりに披露していた。 続いて、黒沢清、是枝裕和両監督が登壇し、東京フィルメックス・ディレクターの林加奈子、プログラムディレクターの市山尚三両氏の進行のもと、フィルメックスの10年の歴史になぞらえて、それぞれの10年を振り返った。昨今の日本映画界の国際化について、是枝監督は、新作『空気人形』(2009)で、主役に韓国のペ・ドゥナ氏、カメラマンに台湾のリー・ピンビン氏と外国人を起用しているが、特に国際化のようなものを意識していたわけではなく、監督自身がペ・ドゥナ氏のファンで、リー・ピンビン氏とも「いつか一緒にやりたいですね」と言っていたことがきっかけとなり、結果として三カ国語の現場が実現したという。黒沢監督は、つい先日亡くなったオランダ人プロデューサーのバウター・バレンドレヒト氏からの依頼を受けて製作した『トウキョウソナタ』(2008)について、何本かホラー映画が続いていたため、ホラーからかけ離れた作品を撮りたいと思い、周囲に吹聴していたところに「だったら、こんなのどう?」とバレンドレヒト氏が見せてくれたのが『トウキョウソナタ』の原案だったというエピソードに触れ、現場や編集中においても、バレンドレヒト氏からの特別の指示はなく、低予算におさまるという安心感もあり、(おそらくは)信用して任せてくれていたのだと思うと語った。 また、映画のデジタル化については、2000年のカンヌ国際映画祭のオープニング・シンポジウムで「結局、目の前のものをどう撮るかが問題なのであって、それを何で撮るか(デジタルで撮るのか、フィルムで撮るのか)ということを問題にするつもりはない」と語っていたという黒沢監督は、『ドレミファ娘の血は騒ぐ』(1985)の頃からビデオを使っていたこともあり、現場的には、デジタルもフィルムも全く関係ないというところが当時からあり、それは現在もほとんど変わっておらず、『アカルイミライ』(2003)は全部デジタルで撮り、映画館ではフィルムで上映したが、当時はデジタルで撮影しても最終的にはフィルムにしていたという流れの中で、再びフィルムに戻っていくようになり、全部デジタルで撮っていてもフィルム的な質感を狙い、いかにフィルムに近づけていくかというようなことを考えていて、いずれデジタルならではの質感というものを求めるようになっていくのかもしれないと言う。  
一方、TVからキャリアをスタートさせた是枝監督は、「デジタルで撮るのなら、フィルムでは表現できないものをやりたい。ペッタリとした奥行きのない画のほうが自分たちの見ている風景に近いはずだ」と語っていたある監督の話に触れ、自分自身は決してそう思ってはいないけれど、筋は通っていると思ったと語り、黒沢監督が、ある対象物にカメラを向けることが映画の最後の砦だとすれば、現在公開中の『クリスマス・キャロル』などはカメラを向ける対象物がない世界で、それは果たして映画なんだろうかと考えると受けた。結局、フィルムを想定して創ったものをデジタルで上映すると見えなくていいものまでが見えてしまう経験にも触れながら、上映形態の主流がデジタルになるのであれば、製作費の面でもデジタルへの移行は進むだろうし、後は作り手がどう向き合うのかだろうということで問題が締められた。  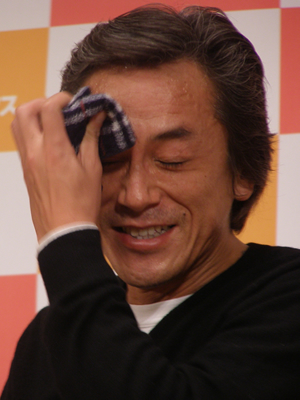
最後に、両監督に俳優の寺島進、西島秀俊の両氏が加わり、映画とTVの違い、映画の魅力に目覚めたきっかけや映画祭の役割と未来の展望などについて話題を広げ、「昔は映画に出ることは難しく、映画俳優は特別な(変わった)人たちに見えたけれど、今は映画とTVの垣根がなくなってきている」(西島氏)、「自分は2時間ドラマを手がけたこともあるが、特に違いは感じず、TV局の出資作品でも(TVとの親和性を求められることなく)、むしろTVとは違うものをやってくれと言われることが多かった」(黒沢氏)、「子供の頃から映画館は特別な場所で、高校生の頃はよく学校をさぼってATG作品などを観にいった」(寺島氏)、「大学の授業で蓮實重彦氏の『ただおもしろがる域を超えて、あれ、おやと思う瞬間こそ映画を観ている瞬間』との言葉などに影響を受けたが、フィルメックスはそういう映画の宝庫」(黒沢氏)、「広く多様的な作品が取り上げられる映画祭、(ナントなどのように)監督への質問の場面でも、作品について観客同士が議論を交わすような映画祭は素敵だと思う」(是枝氏)、「釜山の映画祭で、(授業をやっているはずの時間帯に)小学生がメインストリートを歩いていたが、学校の先生が映画祭へ行けと言っていたらしい」(寺島氏)、「トリノなどではフェスティバルメニューを用意している食堂の食券が用意されていて、普通ならホテルで済ませてしまいそうなところを、その食券を使える食堂を探しているうちに、必然的に街を歩くことになる」(是枝氏)などの意見が出されていた。 
また、市山尚三プログラムディレクターからは、「映画祭はお祭り。なるべく多様な多くの作品を紹介したい。(フィルメックスでは厳選された本数の作品が用意されているので、できれば)すべての作品を観てもらいたい。始めた時に5年はやろうと思っていたところを10年続けてこられたのはみなさんのおかげ。10年目の節目に今後の展開も考えたい」、林加奈子ディレクターからは、「最初から10〜20年続ける覚悟をしていたが、それだけの年数が経った時に、映画祭がなくてもわかり合えるよう(な世の中)になれば。フィルメックスでしかできないことをやり続け、20年まで続けられたらまたシンポジウムをやってみたい」などと、今後に向けての抱負が語られていた。 |